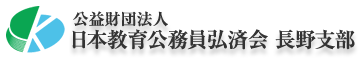研究助成実践事例 2018年度 学校研究助成者一覧 : research grant report

| 2018年度 個人研究助成者一覧 No.1~No.8は優秀論文 以下順不同 敬称略 |
|||
|---|---|---|---|
| No. | 所属校 | 氏名 | 研究テーマ |
| 1 | 伊那市立 手良小学校 | 有賀 祥子 | どの子も「わかる」「できる」「つながる」喜びを感じ「もっとやりたい」という意欲が持てる授業づくり ~協同学習の研究的実践~ |
| 2 | 中野市立 科野小学校 | 松村 貴子 | 音楽を楽しむ子どもたちを育むための音楽指導のあり方 ~歌わない学校から少人数でも大きな声で歌う学校を目指して~ |
| 3 | 長野県 梓川高等学校 | 染野 雄太郎 | 高校生と満蒙開拓団 ~地元の歴史から主体的な学びを考える~ |
| 4 | 松本市立 筑摩野中学校 | 赤堀 聡 | メタ認知としての自己評価を取り入れた国語学習 |
| 5 | 長野市立 青木島小学校 | 鈴木 佳奈子 | 自治的な子どもの話し合いの活動を実現するために ~学級会サイクルの構成と子どもたちの問題解決力の育成に着目して~ |
| 6 | 栄村立 栄小学校 | 石澤 倫雄 | 一人一人が体力作りの課題をもち、進んで体を動かしていく指導のあり方 ~松本大学との連携を通して~ |
| 7 | 飯山市立 飯山小学校 | 高橋 裕之 | 特別支援学級における自立活動の時間を利用した学習活動の実践 ~『さくらショップ』の活動を通してS児から学んだこと~ |
| 8 | 松本養護学校 (寄宿舎) | 酒井 美津子 | 寄宿舎生活を通して、社会生活のルールとマナーを学ぶ |
| 9 | 佐久市立 中込小学校 | 松川 剛史 | 式に表す・式をよむ指導の構想 |
| 10 | 佐久市立 佐久城山小学校 | 福島 明美 | 作文教育を通して大切にしてきたこと |
| 11 | 南牧村立 南牧中学校 | 小林 綾音 | ビギナーが推進する道徳 ―教科化目前教員も生徒も全員で「脱・なんとなく道徳」― |
| 12 | 佐久市立 浅科中学校 | 北原 憲康 | 現代史の教え方 |
| 13 | 東御市立 田中小学校 | 佐原 美佳 | 体験活動を中心とした福祉教育 ~パラリンピックスポーツを通じて考える誰もが関わりあえること~ |
| 14 | 東御市立 北御牧小学校 | 田中 一輝 | 郷土を開く ~八重原台地に水を引く~ |
| 15 | 上田市立 西小学校 | 小宮山 翔平 | 地域素材の教材化 |
| 16 | 上田市立 西小学校 | 茨木 信行 | 野鳥観察を通して自然の見方考え方を深める研究 ~不思議さや巧みさと出会う場の工夫~ |
| 17 | 上田市立 東小学校 | 片岡 宏文 | 夢と希望をもって自己肯定感を育てるために ―児童への講話とPTAへの講話での試み― |
| 18 | 上田市立 塩川小学校 | 島津 紀子 | 敬老園との一年間を通しての交流活動 ~より主体的な子どもたちの姿を目指しての歩み~ |
| 19 | 上田市立 第一中学校 | 五味 房子 | 電子天秤がつなぐ子どもたちの想い ~南アフリカへの支援活動を通して~ |
| 20 | 上田市立 第二中学校 | 小林 実季 | A生の中でつながる学び |
| 21 | 岡谷市立 小井川小学校 | 渡辺 克弥 | 生活科「ネバネバ 大さくせん」 ~納豆づくりの取り組み~ |
| 22 | 岡谷市立 岡谷田中小学校 | 山田 千恵 | 子どもが集中して学習に取り組める授業のあり方 ~授業に参加できない子の支援を柱に~ |
| 23 | 岡谷市立 岡谷田中小学校 | 牛山 千恵子 | 個に向き合うことを通して得られるもの |
| 24 | 岡谷市立 岡谷田中小学校 | 山﨑 みのり | 一人の児童の姿を通して見えてきたこと ~授業改善をめざして~ |
| 25 | 下諏訪町立 下諏訪南小学校 | 山﨑 あかね | 失敗や問題点の発見から、協働的な学びで解決しようとする授業の設定 |
| 26 | 下諏訪町立 下諏訪南小学校 | 市川 元彦 | 「進んでかかわり ともにやりぬく子ども」を育む学校運営 |
| 27 | 諏訪市立 高島小学校 | 原 宏典 | “本物との出会い”が子どもたちにもたらすもの |
| 28 | 茅野市立 豊平小学校 | 宮澤 俊充 | 新しい時代・社会を生きる子どもたちに伝えたいこと |
| 29 | 富士見町立 境小学校 | 植松 航一朗 | 発達障がいのある児童と共に学び合う授業の実現 |
| 30 | 原村立 原中学校 | 平塚 広司 | 原村を知り、原村で学び、原村と生きる生徒を育てる「原村学」 |
| 31 | 富士見町立 富士見中学校 | 岩崎 香織 | 理科における深い学びとは |
| 32 | 伊那市立 東春近小学校 | 土橋 早苗 | 子どもたちが自分の姿や思いを語り合いながら、人権感覚を高めていく道徳学習のあり方 |
| 33 | 駒ケ根市立 赤穂南小学校 | 矢﨑 和美 | 総合的な学習の時間において、国際理解教育を進めるにあたりJICAやWAJと連携・協働してのカリキュラム開発のあり方(実践事例の蓄積) |
| 34 | 箕輪町立 箕輪中学校 | 三澤 裕美 | 「生徒のよさと可能性を発信する」学校だよりの編集の工夫 |
| 35 | 阿南町立 大下条小学校 | 伊藤 俊光 | 文学教材の読解力を高めるための国語学習のあり方 |
| 36 | 阿智村立 浪合小学校 | 久保田 雅樹 | 新学習指導要領における「総合的な学習の時間の目標」の具現化 ~「ふるさとの森林に学ぼう」(5年)の実践事例を通して~ |
| 37 | 天龍村立 天龍中学校 | 岡庭 未貴 | 自ら健康管理できる生徒を育てるための保健教育・保健指導はどうあったらよいか ~掲示物の工夫~ |
| 38 | 泰阜村立 泰阜中学校 | 林 嵩大 | 仲間とかかわり合いながら主体的に活動し、体力と運動技能を高める指導の在り方 |
| 39 | 木曽町立 三岳小学校 | 百瀬 匡 | 1・2年生での「すもう遊び」を実践して ―力試しの運動― |
| 40 | 上松町立 上松小学校 | 大川 雅也 | 「感覚統合」の観点を取り入れた運動メニュー ~通級A児への実践~ |
| 41 | 王滝村立 王滝中学校 | 伊藤 優 | 子どもたちが自ら動きだす音楽授業 ~ドレミパイプの実践を通して~ |
| 42 | 松本市立 開成中学校 | 高山 勝行 | 普通学級での数学の授業における合理的配慮やユニバーサルデザイン化の実践 |
| 43 | 松本市立 菅野中学校 | 北澤 信 | 学校図書館と連携した理科学習環境の充実 ~理科好き生徒を育む一助としての菅野中学校図書館理科室支店の運用~ |
| 44 | 松本市立 会田中学校 | 宮島 雅子 | 生徒会と連携した、健康課題解決のための取り組みについて |
| 45 | 朝日村立 朝日小学校 | 清水 義浩 | 道徳科…考え、議論する授業の構想 ~道徳科におけるアクティブ・ラーニング~ |
| 46 | 筑北村立 筑北小学校 | 丸山 克也 | 教科書のない学習「総合的な学習の時間」での、どの子も楽しく「分かる・できる」を実践するためのよりよい授業改善に向かって |
| 47 | 千曲市立 戸倉小学校 | 大平 君代 | 自閉スペクトラム症のA児が、笑顔で学校生活を送るにはどんな支援をしたらよいか |
| 48 | 千曲市立 埴生小学校 | 小田切 和子 | 子どもがふるさとに愛着をもち、自己肯定感を高めるための活動のあり方 ~「キャリア教育の視点」を大切にした総合的な学習の時間の工夫~ |
| 49 | 千曲市立 更埴西中学校 | 青木 猛 | 「主体的・対話的で深い学び」の授業を目指して ―社会科歴史的事象における授業づくり― |
| 50 | 長野市立 加茂小学校 | 武田 昌之 | 社会の変化に応じた学校の在り方とは、どのようなものか ~特色ある教育現場の様子からの考察~ |
| 51 | 長野市立 加茂小学校 | 小笠原 淳 | 仲間とかかわりながら、互いのよさに気づき認め合う集団作りのあり方 ~「縦割り活動」を通して~ |
| 52 | 長野市立 芹田小学校 | 太田 直樹 | 小学校での「障害理解授業」の実践 ~インクルーシブな学校を目指して~ |
| 53 | 長野市立 吉田小学校 | 加藤 健三 | 限られた空間の中で児童の身体能力を向上させる遊び場つくり |
| 54 | 長野市立 裾花小学校 | 雪入 哲也 | 提案 学年教科担任制で働き方改革 |
| 55 | 長野市立 若槻小学校 | 山中 誠 | 新学習指導要領に則した授業改善のあり方 ~児童の主体的・対話的な学びを通して~ |
| 56 | 長野市立 三陽中学校 | 市川 美紀子 | 生徒の問いが連続する探究学習のあり方 |
| 57 | 長野市立 広徳中学校 | 髙野 勉 | 生徒が自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考える能力を高めるためには、どのように教材を組織し指導したらよいか |
| 58 | 高山村立 高山小学校 | 清水 海亜 | 友だちと関わりながら運動や遊びの楽しさを味わい、一人ひとりが満足感を得られる授業づくり ~体力の向上を視点に入れた指導を通して~ |
| 59 | 須坂市立 小山小学校 | 酒井 美旺 | 自ら追究する子どもを育てるための、学級での動物飼育について |
| 60 | 山ノ内町立 東小学校 | 宮尾 匠 | 自ら問いを見いだし、課題解決のために友と協力して、考えたことを表現できる子どもの育成 ~ICT機器の効果的な活用を考えることを通して~ |
| 61 | 山ノ内町立 東小学校 | 竹内 雅人 | 互いに聴き合い学び合い「できた」「わかった」という実感を高めるための指導のあり方 ~友だちと伝え合って~ |
| 62 | 木島平村立 木島平小学校 | 丸山 幸恵 | 人をつなぐことで、チーム支援を活性化させる「養護教諭」「保健室」のあり方 |
| 63 | 中野市立 中野小学校 | 市川 麻衣子 | 友と共に、生き物(やぎ)とより深く関わるための支援のあり方 |
| 64 | 中野市立 中野小学校 | 土屋 英彦 | 対象と向き合い、思考しながら学ぶ環境づくり |
| 65 | 中野市立 豊井小学校 | 岩田 伊令 | 人々の営みに焦点を当てた社会科学習と総合的な学習の時間が相互に活きる授業づくり |
| 66 | 山ノ内町立 山ノ内中学校 | 清水 まゆみ | 主体的な表現追究を実現していくことができる生徒の育成 |
| 67 | 栄村立 栄小学校 | 宇佐美 昌博 | 遠隔共同学習で育まれる資質・能力に関する考察 ~日常的・継続的な実践を通して~ |
| 68 | 栄村立 栄小学校 | 藤沢 佳那 | 児童によるオペレッタづくりの実践を通して ~生活科の実践を基に合科的に学ぶ中で、音楽の資質・能力を高める指導~ |
| 69 | 飯山市立 秋津小学校 | 上松 由香里 | 段階的に「協力」する体験型学習を通して、どの子も安心して過ごせる学級づくりを目指して |
| 70 | 飯山市立 飯山小学校 | 德永 吉彦 | ヤギとのくらしの中で、自分自身の在り方を問い直し、その姿に謙虚に向き合っていく子どもたち ~動物飼育の実践から~ |
| 71 | 飯山市立 泉台小学校 | 荒井 彰平 | 子どもの困り感に寄り添った教師・友だちの支援のあり方 ~どの子も意欲的に追究しようとする支援のあり方~ |
| 72 | 飯山市立 常盤小学校 | 武田 彰子 | お互いのよさや違いを認め合い、よりよい人間関係を築こうとしていく人権教育のあり方 |
| 73 | 飯山市立 常盤小学校 | 田牧 諒 | 「むずかしそう」を「おもしろそう」に! ~子どもに確かな力をつける 説明文の授業づくり~ |
| 74 | 飯山市立 東小学校 | 中村 大 | 一人ひとりの思いを大切にした学びをつなげていく授業づくり ~対話的な話し合い活動からスタートする総合的な学習の時間を手掛かりにして~ |
| 75 | 飯山市立 木島小学校 | 中村 晃子 | イメージと音を結びつけて考える音楽作り |
| 76 | 飯山市立 城北中学校 | 安田 貢 | 思考力を高める「計測と制御」の教材開発と授業実践 |
| 77 | 飯山市立 城北中学校 | 田中 昭道 | 学び合う授業の充実に向けた校長としての学校経営のあり方 |
| 78 | 大町市立 美麻小中学校 | 宮澤 美帆子 | 「知っている英語」から「使える英語」へ ~協働の学びの良さを最大限に生かして~ |
| 79 | 長野県 小諸養護学校 (ゆめゆりの丘分教室) | 佐藤 充志 | 児童生徒のねがいや困り感に寄り添った「人とのかかわり」への指導支援はどうあったらよいか ~様々な視点からの実態把握を活かして~ |
| 80 | 長野県 諏訪養護学校 (寄宿舎) | 宮澤 賢一 | その子に合った安心できる場所、ひと、もの(活動)+見通しがもてる生活づくりを通して、個別の指導計画による指導・支援とキャリア教育の実践 ~初めて寄宿舎を利用する自閉症生徒の事例から~ |
| 81 | 長野県 諏訪養護学校 (寄宿舎) | 樋口 勝治 | 「本人の願い」に基づいた具体的な支援はどうあったらよいか |
| 82 | 長野県 諏訪養護学校 (寄宿舎) | 石松 恭輔 | 生活場面ごとに、一人でできる事が増えるための支援はどうあったらよいか |
| 83 | 長野県 諏訪養護学校 (寄宿舎) | 中村 美香 | 周囲の声がけを頼りにして行動する生徒が、自ら取り組めるようになるための支援とは |
| 84 | 長野県 花田養護学校 | 鬼頭 真紀恵 | 「伝えたい」「やりたい」と思う授業づくり |
| 85 | 長野県 花田養護学校 | 宮澤 史生 | 生き生きと活動するための授業づくりを考える |
| 86 | 長野県 花田養護学校 | 山本 常徳 | 教師の成長、職場の成長、子どもの成長のために今できることは何か |
| 87 | 長野県 飯田養護学校 | 林 愛 | 摂食指導の実際 ~安全に、そして楽しく、主体的に食べるには~ |
| 88 | 長野県 飯田養護学校 | 小室 惟 | 視線入力学習を通して、重度重複障害のある児童生徒の「見る力」を伸ばす ―コミュニケーションへのステップとして― |
| 89 | 長野県 飯田養護学校 | 丸山 裕也 | 生徒が見通しを持って取り組める作業的要素の学習について |
| 90 | 長野県 木曽養護学校 | 荒井 奈央 | 日常生活に生かせる授業作り ~日々の子どもたちの姿から~ |
| 91 | 長野県 安曇養護学校 (寄宿舎) | 宮澤 健一 | 特別支援学校寄宿舎において日常生活の会話記録の蓄積が言語力を育て、生活力の向上につながることを検証する |
| 92 | 長野県 安曇養護学校 (寄宿舎) | 橋詰 薫夫 | 特別支援学校寄宿舎において日常生活の会話記録の蓄積が言語力を育て、生活力の向上につながることを検証する |
| 93 | 長野県 安曇養護学校 (寄宿舎) | 蓑手 希代子 | 特別支援学校寄宿舎において日常生活の会話記録の蓄積が言語力を育て、生活力の向上につながることを検証する |
| 94 | 長野県 松本盲学校 (寄宿舎) | 丸山 晴美 | A生のコミュニケーション能力の向上をめざして |
| 95 | 長野県 松本盲学校 (寄宿舎) | 長田 正樹 | S生の見え方に応じた、身辺整理の支援の方法について |
| 96 | 長野県 松本盲学校 | 西川 澄 | 光覚活用幼児の環境把握にかかわる学習 ~歩行学習と個別学習に視点をあてて~ |
| 97 | 長野県 松本盲学校 | 日野 瑠里 | 自分と他者に対する基本的信頼感を養うための実践 ~全盲の高校生と幼稚部の交流~ |
| 98 | 長野県 松本ろう学校 | 北澤 千枝 | 「自分ごと」として学び合う部研究を目ざして |
| 99 | 長野県 松本ろう学校 (寄宿舎) | 三溝 浩章 | 卒業後の生活に必要な力を見極め、定着していくための支援のあり方 |
| 100 | 長野県 松本ろう学校 | 湯本 友里香 | 相手意識を育て、やりとりをする力をのばす ~二次的ことばの習得を目指して~ |
| 101 | 長野県 松本ろう学校 | 筒井 裕子 | 卒業後の生活を見据えた高等部生の支援はどうあったらよいか ~一緒に働きたいと思われる生徒の育成を目ざして~ |
| 102 | 長野県 松本養護学校 (寄宿舎) | 小澤 さくら | 安心して生活ができるための支援を探る |
| 103 | 長野県 松本養護学校 (寄宿舎) | 植松 美千代 | 集団生活の中で、将来につながるための支援のあり方を探る ~コミュニケーション面での支援~ |
| 104 | 長野県 松本養護学校 (寄宿舎) | 小口 訓亮 | 舎生の思いをくみ取るための支援の在り方 |
| 105 | 長野県 松本養護学校 | 笠原 律子 | 一人ひとりの主体的な姿を導くための授業づくりのあり方 ~児童生徒の実態「思い」「願い」のとらえから個々に応じた支援のあり方~ |
| 106 | 長野県 松本養護学校 | 松澤 敦子 | 一人ひとりが主体的に取り組む姿を目指した授業づくり ~「ねがい」を達成するための支援のあり方~ |
| 107 | 長野県 稲荷山養護学校 更級分教室 | 田本 明子 | 特別支援学校分教室の生徒が満足感・充実感を実感できる学習場面の設定と支援の工夫 ~外国語の授業を通して~ |
| 108 | 長野県 稲荷山養護学校 更級分教室 | 大峽 諭 | 作業学習 ビルクリーニングを通しての働く力の育成 |
| 109 | 長野県 長野盲学校 | 栁澤 英子 | 見え方に配慮を要する児童・生徒の特性をとらえた指導、支援はどうあったらよいか ~視覚障がいと発達の偏りをあわせもつ児童の指導・支援のあり方について~ |
| 110 | 長野県 長野盲学校 | 倉井 真理子 | 鍼実技指導における指導内容とリスク管理 |
| 111 | 長野県 長野盲学校 | 社納 龍太 | 臨床実習における電子カルテ導入に向けた取り組み |
| 112 | 長野県 長野盲学校 | 中島 茂典 | 長盲式あん摩教本「腹臥位での全身按摩(50分)」の改訂について |
| 113 | 長野県 長野盲学校 | 越 久子 | 点字学習の導入に向けてのレディネス形成のための支援はどうあったら良いか |
| 114 | 長野県 長野盲学校 | 新井 賢治 | 知的障がい特別支援学校児童生徒の視力検査に関する調査 |
| 115 | 長野県 長野盲学校 (寄宿舎) | 若林 公子 | 生きる力を育てる寄宿舎の支援はどうあったらよいか |
| 116 | 長野県 長野盲学校 (寄宿舎) | 植木 隆市 | 将来に役立つ生活技術を習得するために ~食についての学びや調理活動を通して~ |
| 117 | 長野県 長野ろう学校 (寄宿舎) | 小川 廣美 | 自立に向けたコミュニケーション能力を高めていく指導のあり方 ~個別の指導計画の作成・活用・共有~ |
| 118 | 長野県 長野ろう学校 | 中村 佑夏 | 自分の考えをもてる子どもを育てるための指導はどうあったらよいか ~ことばで考えて ことばで伝える~ |
| 119 | 長野県 長野ろう学校 | 村上 清佳 | 子どもの思いを受け止め、子どもが思いをことばにするために、教師はどうあったらよいか ―話し合い活動を通して― |
| 120 | 長野県 長野ろう学校 | 岩田 和幸 | 思考する力を高めるための教科指導のあり方 |
| 121 | 長野県 長野養護学校室 | 山口 綾子 | 生徒たちが毎日の生活に自分からめいっぱい取り組むためのできる状況づくり ~アセスメントに基づいた教育課題の設定と個別の課題学習のあり方を通して~ |
| 122 | 長野県 長野養護学校 | 田中 千恵 | 児童生徒の「やりたい」を実現する、個別の時間とほほえみタイムの連携のありかた ~個別の時間の姿をいかした活動の場作り~ |
| 123 | 長野県 長野養護学校 | 牧内 寛 | 生徒が製品作りに『自分から、自分で、めいっぱい』取り組むための作業学習のあり方 ~『できる状況づくり』に視点をあてて~ |
| 124 | 長野県 長野養護学校 朝陽教室 | 小山 聖子 | 特別支援学校高等部卒業生の進路 ~障がい者雇用促進法改正と朝陽教室の生徒の事例より~ |
| 125 | 長野県 長野養護学校 すざか分教室 | 諸戸 恵美子 | 生徒が主体的に活動する授業づくり ~地域を舞台にしたビルメンテナンス作業を通して~ |
| 126 | 長野県 若槻養護学校 | 深澤 雅子 | アセスメントを生かした授業づくり ~キャリア教育の視点から~ |
| 127 | 長野県 飯山養護学校 | 矢髙 歩美 | 一人ひとりの良さや可能性を理解し、個の特性や発達段階にあったコミュニケーションを考える ~写真や絵カード、ICTを用いたコミュニケーション・視覚支援の在り方の追究~ |
| 128 | 長野県 飯山養護学校 | 近藤 貴幸 | 今ある力をもとに、自分から取り組みたくなるような運動作りと健康と体力向上を目指した体育学習の工夫 ~体育プロブラムへの工夫と個に応じた支援~ |
| 129 | 長野県 望月高等学校 | 井出 百合子 | 望月学の取り組み ~地方から学ぶ・地域と共に学ぶ~ |
| 130 | 長野県 野沢北高等学校 | 畠山 啓吾 | 人間の身体を流れる電流の実験 ~友達みんなで手をつないで、メロディICの音楽を流そう~ |
| 131 | 長野県 上田千曲高等学校 | 小池 昌信 | 簡易型基板加工機の制作 |
| 132 | 長野県 上田高等学校 | 髙栁 剛士 | 風景画の構図について |
| 133 | 長野県 諏訪清陵高等学校 | 北原 司 | 「エレガントな答案作成を目指して」でも想定外の生徒の反応 ―プレゼンテーション能力の形成への実践― |
| 134 | 飯田女子高等学校 | 湯澤 直人 | 無尽の研究 ―飯田下伊那地方の無尽の特徴と、その教材化の可能性― |
| 135 | 長野県 木曽青峰高等学校 | 日下部 英司 | BREAK THROUGH! センター試験国語 ~センター試験国語における解法の着眼点を、受験生の目線で考える |
| 136 | 長野県 塩尻志学館高等学校 | 宮入 清志 | ワイン用ぶどうの一番果および二番果の摘房の及ぼす影響 |
| 137 | 長野県 豊科高等学校 | 前田 拓哉 | 大きな写真で伝える昆虫の魅力 |
| 138 | 長野県松本筑摩高等学校 | 櫻井 幸子 | 若年妊娠の実態と就学支援・最新の性教育事情についての研修報告 |
| 139 | 長野県 中野西高等学校 | 町田 達也 | 社会的事象を深化し、時代の転換点をとらえる社会科教育の実践 ~中高連携を目指した授業づくり~ |
| 140 | 戸隠地質化石博物館 | 田辺 智隆 | 「石ころ」から自然を学ぶ意欲をひきだす ―博物館と小学校とで協力した教材化― |